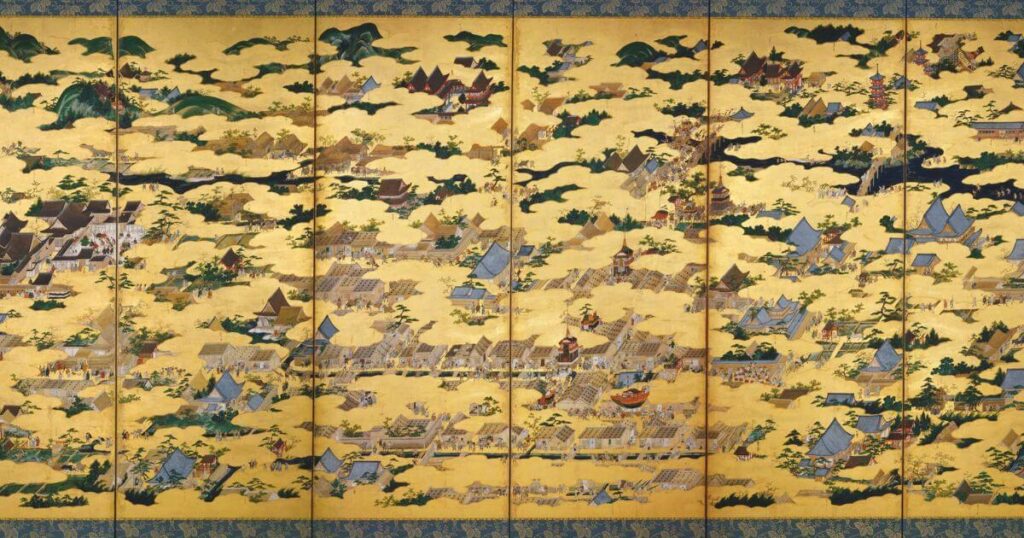三河徳川家– category –
-

夏目 広次(なつめ ひろつぐ)
生年1518年没年1573年主君徳川家康拠点・知行三河官位・役職幼名法名別名正吉、吉信、廣次、次郎左衛門尉 【夏目広次の家族構成】 父夏目吉久母水野家の娘兄弟... -

本多 正信(ほんだ まさのぶ)
生年1538年没年1616年主君徳川家康→松永久秀→徳川家康拠点・知行相模玉縄官位・役職従五位下・佐渡守幼名法名別名正保、正行、弥八郎、本多佐渡 【本多正信の家... -

石川 数正(いしかわ かずまさ)
生年1533年没年1592年または1593年主君徳川家康→豊臣秀吉拠点・知行信濃深志城官位・役職従五位下・伯耆守幼名助四郎法名箇三寺別名康輝、吉輝、与七郎、伯... -

松平 家忠(まつだいら いえただ)
出典:Wikipedia:松平家忠像 生年1555年没年1600年主君徳川家康拠点・知行武蔵忍城官位・役職幼名法名別名又八、又八郎、主殿助 【松平家忠の家族構成】 父松... -

松平 康忠(まつだいら やすただ)
生年1546年没年1618年主君徳川家康→徳川信康→徳川家康→徳川秀忠拠点・知行三河官位・役職幼名法名源斎別名源七郎、上野介 【松平康忠の家族構成】 父松平政忠母... -

服部 半蔵(はっとり はんぞう)
出典:Wikipedia 生年1542年没年1597年主君徳川家康拠点・知行遠江官位・役職石見守幼名法名別名正成、弥太郎、半三、鬼半蔵 【服部半蔵の家族構成】 父服部保... -

平岩 親吉(ひらいわ ちかよし)
出典:Wikipedia:平田院所蔵 生年1542年没年1612年主君徳川家康→徳川義直拠点・知行上野厩橋城官位・役職従五位下・主計頭幼名法名別名七之助 【平岩親吉の家... -

渡辺 守綱(わたなべ もりつな)
出典:Wikipedia:絹本著色渡辺半蔵守網像(愛知県指定文化財、豊田市・守綱寺所蔵) 生年1542年没年1620年主君徳川家康→徳川義直拠点・知行武蔵比企官位・役職... -

鳥居 忠広(とりい ただひろ)
生年不明没年1573年主君徳川家康拠点・知行三河官位・役職幼名法名別名直忠、四郎左衛門 【鳥居忠広の家族構成】 父鳥居忠吉母兄弟忠宗、本翁意伯、元忠、忠広正室... -

鳥居 元忠(とりい もとただ)
出典:Wikipedia:鳥居元忠像(栃木・常楽寺蔵) 生年1539年没年1600年主君徳川家康拠点・知行下総矢作城官位・役職幼名法名別名彦右衛門尉 【鳥居元忠の家族構...