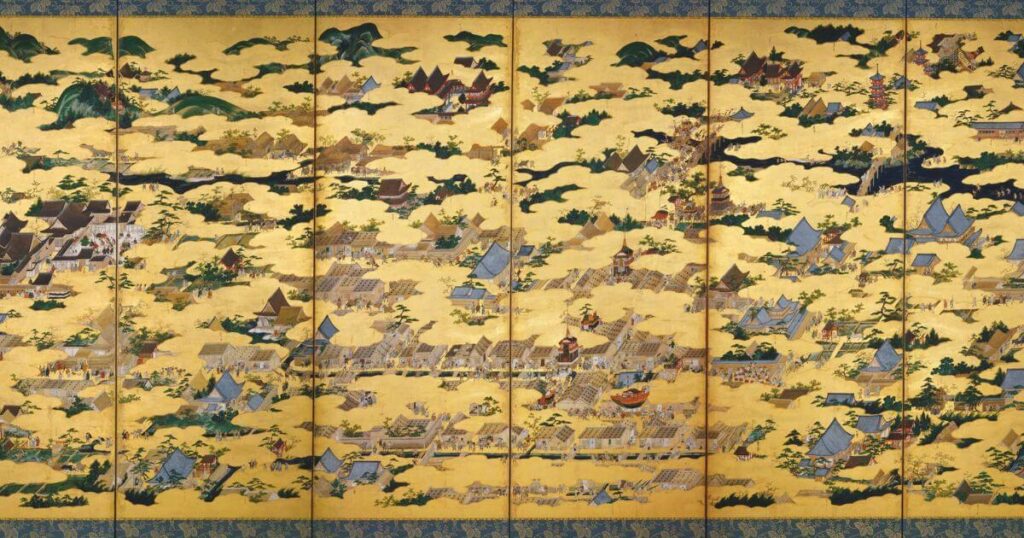関白豊臣家– category –
-

長束 正家(なつか まさいえ)
生年1562年没年1600年主君丹羽長秀→豊臣秀吉→豊臣秀頼拠点・知行近江岡山城官位・役職従五位下・大蔵大輔、従四位下・侍従幼名法名別名新三郎、利兵衛 【長束正... -

増田 長盛(ました ながもり)
出典:Wikipedia:国立国会図書館蔵 生年1545年没年1615年主君豊臣秀吉→豊臣秀頼拠点・知行大和郡山城官位・役職従五位下・右衛門少尉幼名法名別名仁右衛門 【... -

前田 玄以(まえだ げんい)
出典:Wikipedia:前田玄以像(蟠桃院蔵) 生年1539年没年1602年主君織田信長→織田信雄→豊臣秀吉→豊臣秀頼拠点・知行丹波亀山城官位・役職民部卿法印幼名法名玄... -

浅野 長政(あさの ながまさ)
出典:Wikipedia:浅野長政像(東京大学史料編纂所蔵) 生年1547年没年1611年主君織田信長→豊臣秀吉→豊臣秀頼→徳川家康→徳川秀忠拠点・知行甲斐甲府城官位・役... -

石田 三成(いしだ みつなり)
出典:Wikipedia:東京大学史料編纂所所蔵 生年1560年没年1600年主君豊臣秀吉→豊臣秀頼拠点・知行近江佐和山城官位・役職従五位下・治部少輔幼名佐吉法名別名三... -

糟屋 武則(かすや たけのり)
出典:Wikipedia:「太平記英勇伝五十八:糟屋内膳正武則」(落合芳幾作) 生年1562年没年不明主君別所長治→豊臣秀吉→豊臣秀頼→徳川家康拠点・知行播磨加古官位・役... -

脇坂 安治(わきざか やすはる)
出典:Wikipedia:龍野神社蔵の肖像画 生年1554年没年1626年主君浅井長政→明智光秀→豊臣秀吉→豊臣秀頼→徳川家康→徳川秀忠拠点・知行伊予官位・役職従五位下・中... -

加藤 嘉明(かとう よしあき)
出典:Wikipedia:加藤嘉明像(藤栄神社蔵) 生年1563年没年1631年主君羽柴秀勝→豊臣秀吉→豊臣秀頼→徳川家康→徳川秀忠→徳川家光拠点・知行伊予正木城官位・役職... -

平野 長泰(ひらの ながやす)
出典:Wikipedia:「太平記英勇伝七十一:平野権平長康」(落合芳幾作) 生年1559年没年1628年主君豊臣秀吉→豊臣秀頼→徳川秀忠→徳川家光拠点・知行大和官位・役... -

片桐 且元(かたぎり かつもと)
出典:Wikipedia:片桐且元像(模写、大徳寺玉林院所蔵) 生年1556年没年1615年主君浅井長政→豊臣秀吉→豊臣秀頼→徳川家康拠点・知行大和竜田城官位・役職従五位...
12